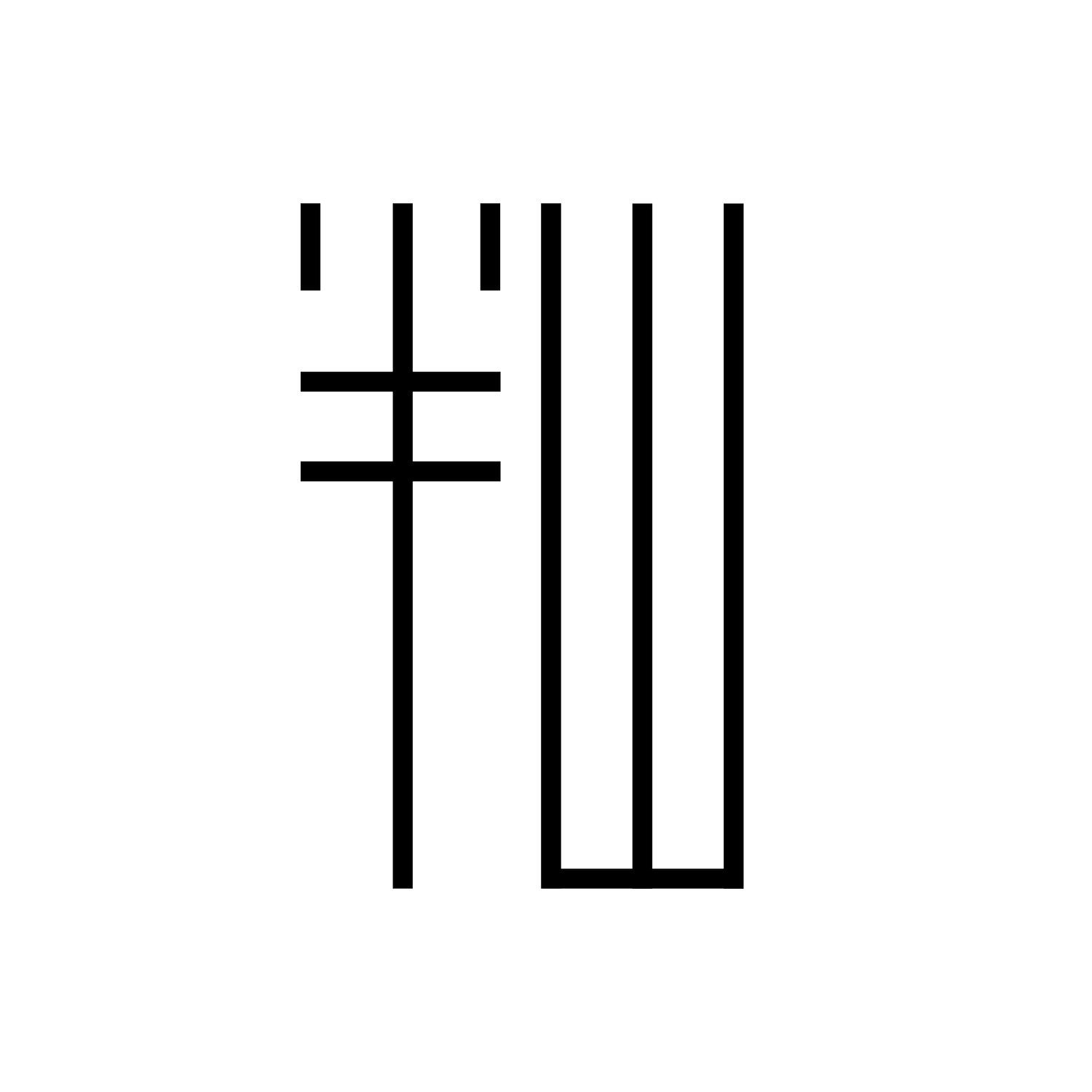このたび、諸般の事情により、私たちは年初に慎重な検討を重ねた結果、半山ギャラリーを2025年4月初旬をもちまして閉廊することになりました。
これに先立ち、3月には最後の展覧会を無事に終了いたしましたことをご報告申し上げます。
2019年8月の開廊以来、約6年にわたり、半山ギャラリーは映像写真表現の可能性を追求し続けてまいりました。展覧会の企画・開催、写真賞の運営、ワークショップの実施など、多岐にわたる活動を通じて、国内外の多くの優れたアーティストや鑑賞者の皆さまと出会い、貴重な時間を共有できましたことを心より光栄に思っております。
このたびの閉廊は誠に残念ではございますが、ここまで活動を継続することができましたのは、ひとえに皆さまからの温かいご支援とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。
この別れが、春の訪れのように、終わりではなく新たな始まりとなりますことを、心より願っております。
半山ギャラリー
2025年4月